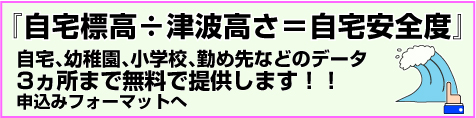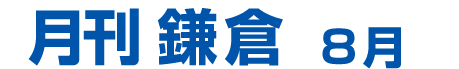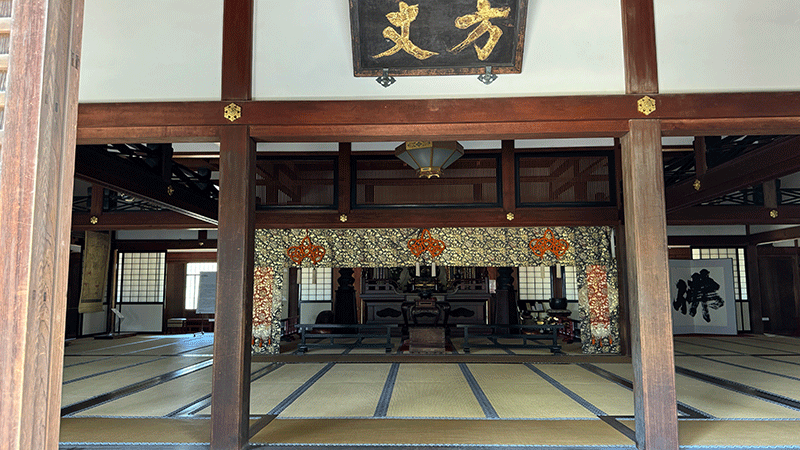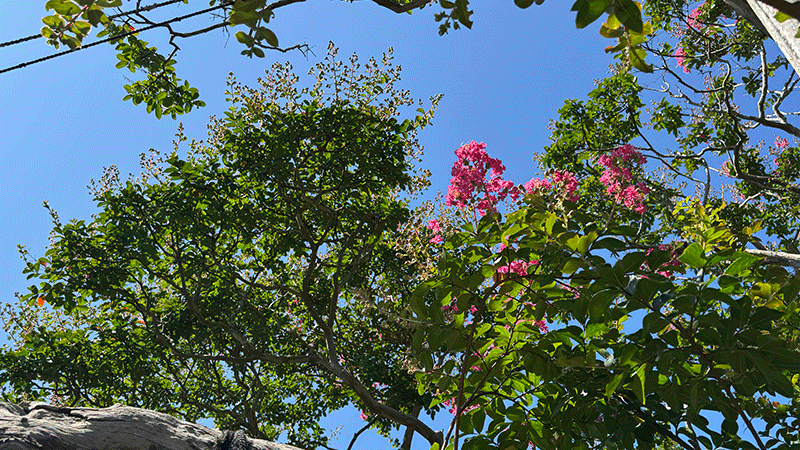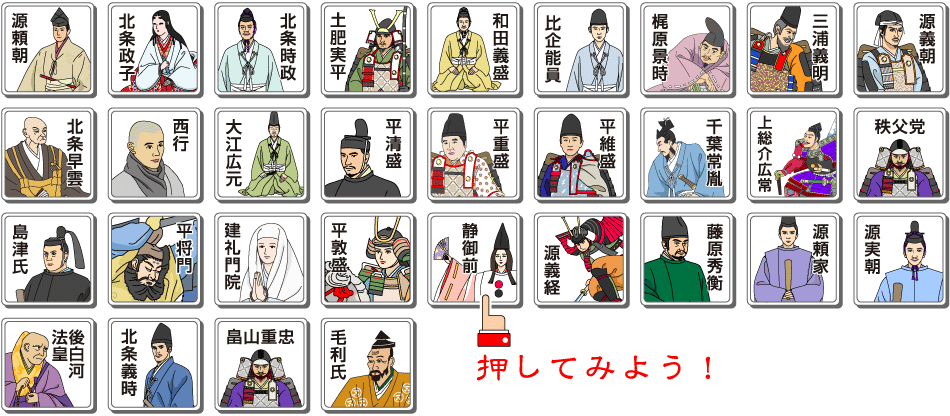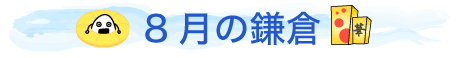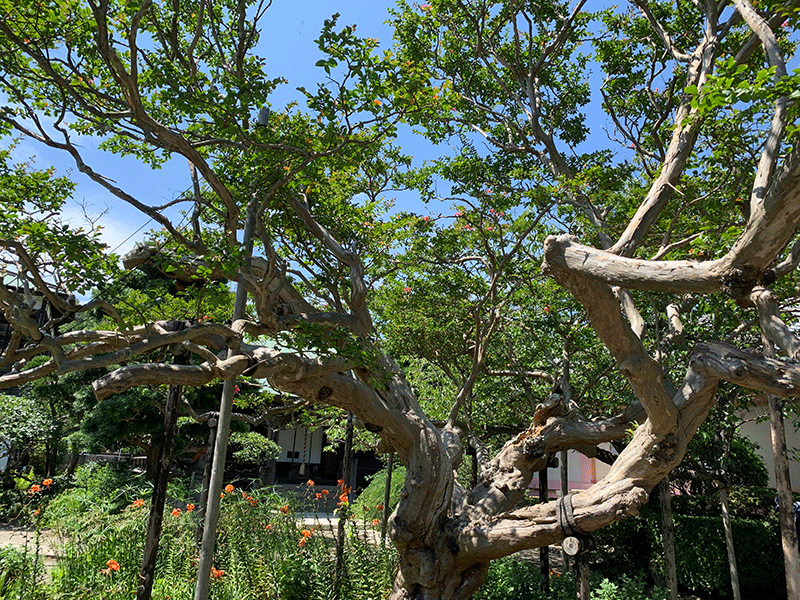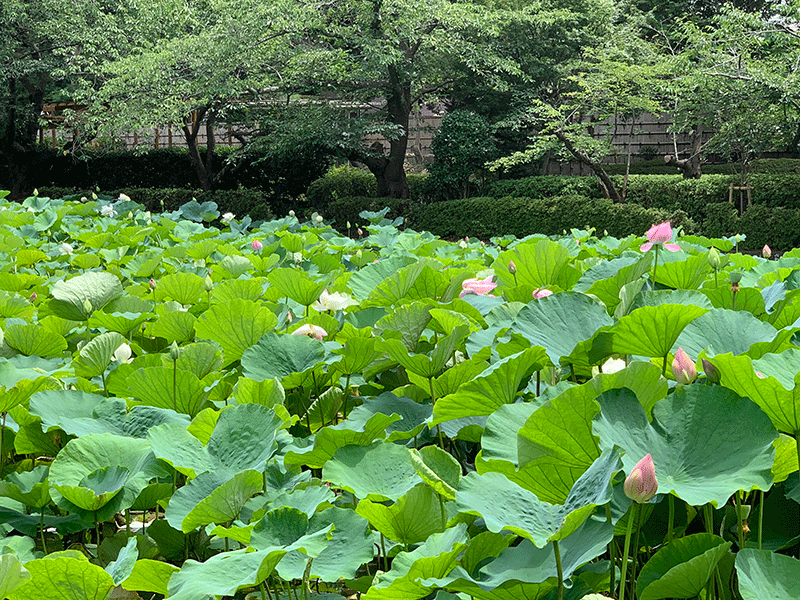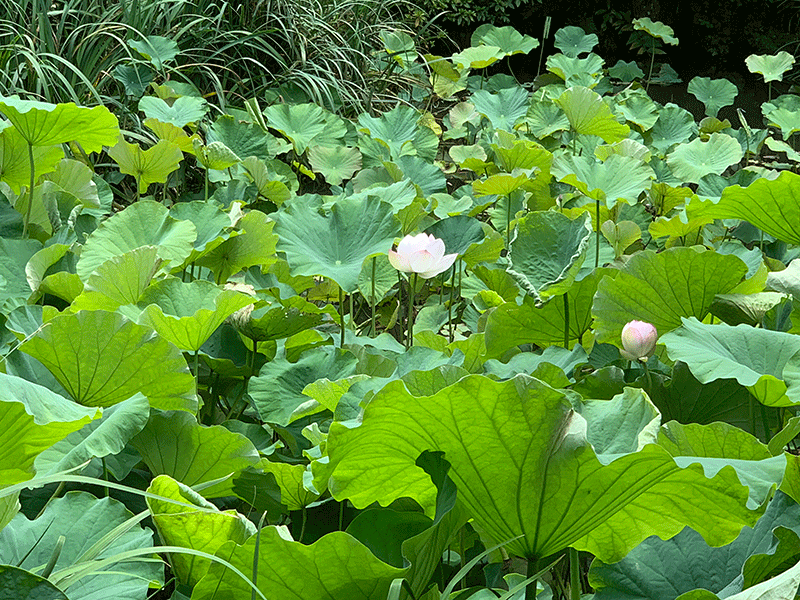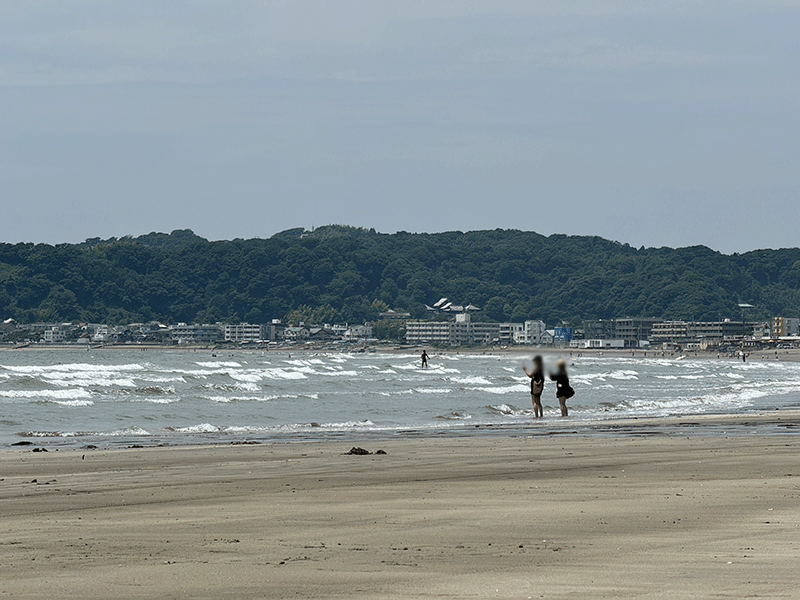開催イベントの中止や延期がある可能性がございます。おでかけの際は事前にご確認ください。
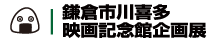
企画展
「開館15周年記念
鎌倉・川喜多邸を訪れた映画人」
2025年8月2日~11月24日
料金:一般300円/小・中学生150円
<映画上映2025年8月〜>
■親子で映画を楽しもう!
夏休みの映画館
『北極のムーシカミーシカ』
8月9日
対象:お子様と保護者
料金:無料※保護者の方は入館料(300円)が必要です。
監督:勝井千賀雄
原作:いぬいとみこ
監修:手塚治虫
声の出演:菅谷政子、野沢雅子、大山のぶ代、松金よね子、古谷徹
■安城家の舞踏会
8月14日、16日
監督:吉村公三郎
出演:原節子、滝沢修、森雅之、逢初夢子、清水将夫、津島惠子
■帰郷
8月14日、17日
監督:大庭秀雄
出演:佐分利信、木暮実千代、津島惠子、三宅邦子、山村聰、徳大寺伸
■わが青春に悔なし
8月15日、17日
監督:黒澤明
出演:原節子、藤田進、大河内傅次郎、杉村春子、三好栄子、河野秋武
■戦争と平和
8月15日、16日
監督:山本薩夫、亀井文夫
出演:池部良、岸旗江、伊豆肇、菅井一郎、島田敬一、藤間房子
■太陽がいっぱい[4Kレストア版]
8月26日、27日、29日、30日
監督:ルネ・クレマン
出演:アラン・ドロン、モーリス・ロネ、マリー・ラフォレ
■太陽はひとりぼっち
8月26日、28日、29日、31日
監督:ミケランジェロ・アントニオーニ
出演:モニカ・ヴィッティ、アラン・ドロン、フランシスコ・ラバル
■サムライ
8月27日、28日、30日、31日
監督:ジャン=ピエール・メルヴィル
出演:アラン・ドロン、ナタリー・ドロン、カティ・ロジェ、フランソワ・ペリエ

■海水浴場の開設
開催場所:材木座海水浴場/
由比ガ浜海水浴/腰越海水浴場
開催日:2025年7月1日〜8月31日
■ぼんぼり祭り
開催場所:鶴岡八幡宮
開催日:8月6日~9日
夏越祭 8月6日 15:00〜
立秋祭 8月7日 17:00〜
実朝祭 8月9日 10:00〜
■四万六千日
開催日:8月10日
開催場所:
●長谷寺
当日のみ、4時~8時まで拝観料無料
●杉本寺
0時~16時まで
護摩供6:00~
大法要10:00~
●安養院
当日のみ、5時~9時まで拝観料無料
■黒地蔵縁日
開催場所:覚園寺
開催日:8月10日
■鎌倉宮例大祭
開催場所:鎌倉宮
開催日:8月19日~21日
8月19日 例祭前夜祭 16:00〜
8月20日 例祭 11:00〜
8月21日 後鎮祭 10:00〜
※2025年8月19日・20日の18:30頃から盆踊り(夜店あり)が行われます

【鎌倉文学館】
鎌倉文学館は2023年3月27日から2027年3月31日(予定)で庭園も含め、大規模改修のため全館休館
【鎌倉市鏑木清方記念美術館】
■企画展「《朝夕安居》大解剖!
~清方えがく、夏の暮らし~」
会期:2025年7月5日~8月24日
開館時間:9:00 ~ 17:00
※最終入館は30分前まで
休館日:毎週月曜日(7月21日、8月11日は開館、7月22日、8月12日
入館料:一般 300円/小・中学生 無料
【神奈川県立近代美術館 鎌倉別館】
■ これもさわれるのかな?
—彫刻に触れる展覧会Ⅱ—
会期:2025年8月2日~10月19日
開館時間:9:30 ~ 17:00
(入館は午後4時30分まで)
休館日:月曜日(8月11日、9月15日、10月13日を除く)
入館料:一般 250円/20歳未満・学生 150円/65歳以上・高校生100円
【神奈川県立近代美術館 葉山館】
■上田義彦 いつも世界は遠く、
会期:2025年7月19日~11月3日
開館時間:9:30 ~ 17:00
(入館は午後4時30分まで)
休館日:月曜日(7月21日、8月11日、9月15日、10月13日、11月3日を除く)
入館料:一般 1200円/20歳未満・学生 1050円/65歳以上 600円/高校生 100円
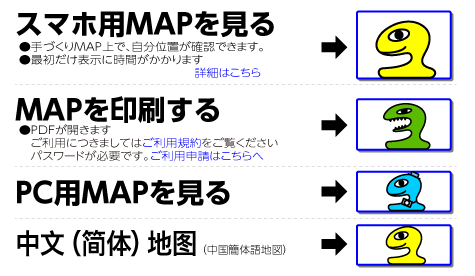
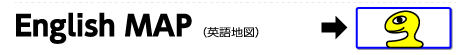


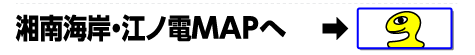
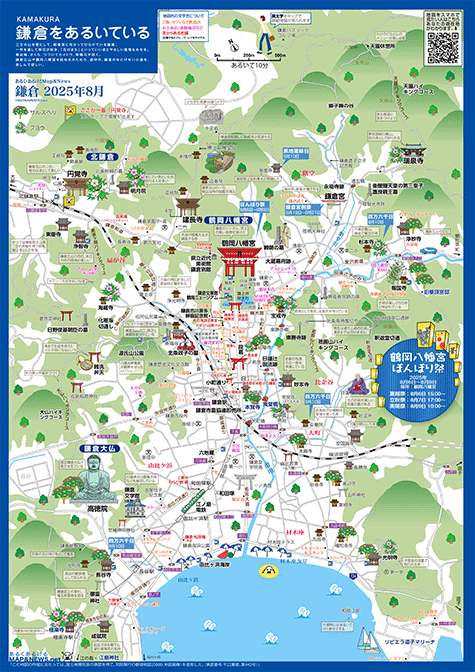
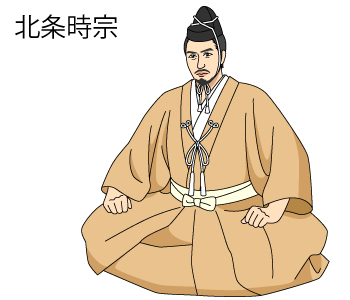 鎌倉幕府八代執権・北条時宗(1251-1284)は蒙古軍の二度(1274年と1281年)の襲来に耐え退けた武士の頭領である。
鎌倉幕府八代執権・北条時宗(1251-1284)は蒙古軍の二度(1274年と1281年)の襲来に耐え退けた武士の頭領である。