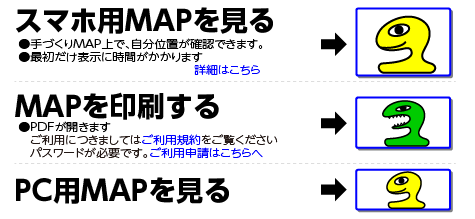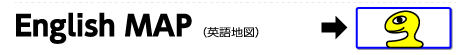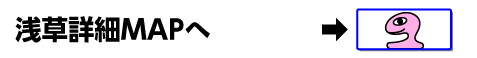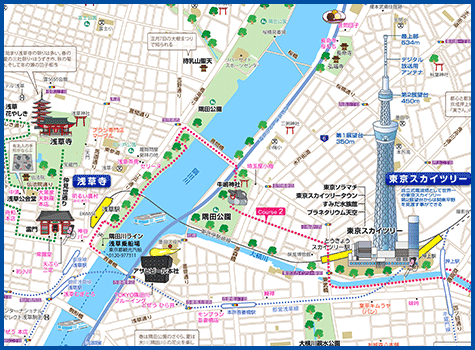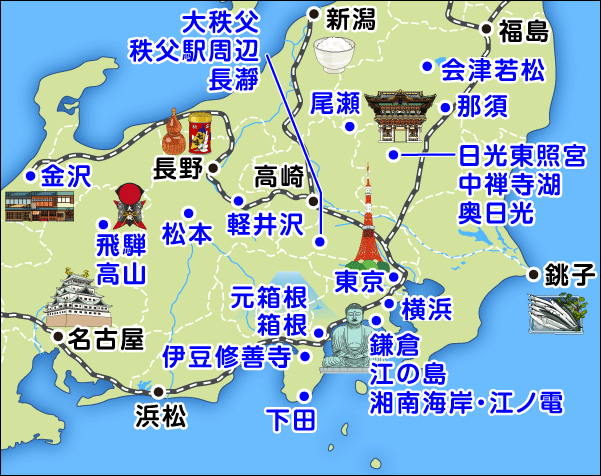香をたき身を清めてお詣りする浅草寺
 本堂
本堂
 香炉
香炉
 宝蔵門・五重塔
宝蔵門・五重塔
 雷門
雷門
浅草寺にお詣りする時。雷門で一礼。写真を撮る。仲見世(参道)を進み宝蔵門。記念写真。お水舎(おみずや)で手を洗い常香炉でお香を浴びて身を清める。本堂の階段を登る。お賽銭を入れて合掌!一礼。心に思っていることをお願いする。お願いするとそれが叶いますよ。 |
江戸・浅草/老舗の多い町並み
浅草は江戸下町の風習、風俗と職人の「技」が受け継がれる町で、技が作り出した商品や芸を売っている。
職人は和食・和菓子・和服などいま人気の技をもつ職人とそば打ちや豆腐職人、さらに花火師や落語家、浪曲師などと畳職人、指物師、刃物師のように玄人受けすjる職人まで多くの人が含まれている。
浅草はいまも職人たちが町に溢れスタスタと歩いている風情がある。彼らが作り出すモノを商う老舗、彼らの芸を見せたり聞かせたりする老舗に行くといい。
触ったり使ってみたり味わったりしながら歩くのが楽しいゾ!
|
どぜう飯田屋
 場所:かっぱ橋本通り
場所:かっぱ橋本通り
安くてうまいどぜうを食わせる店。まるまるのどぜうは苦手という人に骨を抜いたどぜう鍋や蒲焼もある。
幕末に創業したというから150年を超えて暖簾を守っていることになる。
|
職人技が支える老舗/文扇堂
 場所:仲見世通り西へ入る
場所:仲見世通り西へ入る
職人が支える老舗文扇堂、扇子そのものが存在を主張することはあまりない。しかし扇子が小道具として印象に残る場面はある。
今川義元の大軍に攻められ、桶狭間で決戦を挑む時、信長は清州で「人間五十年 下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり」と敦盛を舞う。その時の扇子は生きていた。
落語家が蕎麦を手繰る動作をするときの扇子も印象的か。
|
ジャンボめろんぱん/花月堂 本店・雷門店
 雷門店
場所:本店/西参道・雷門店/仲見世通り西へ入る
雷門店
場所:本店/西参道・雷門店/仲見世通り西へ入る
浅草で5つの店を展開する花月堂。独自の製法でふわふわのメロンパンを作ったという(花月堂のweb参照)。近頃、町を行く若い人のほとんどがメロンパンをぱくぱく食べている。
|